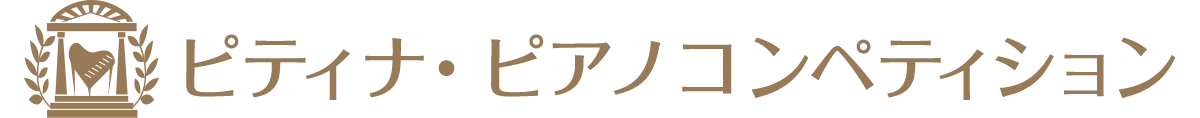レッスンを活性化する指導者による演奏の力
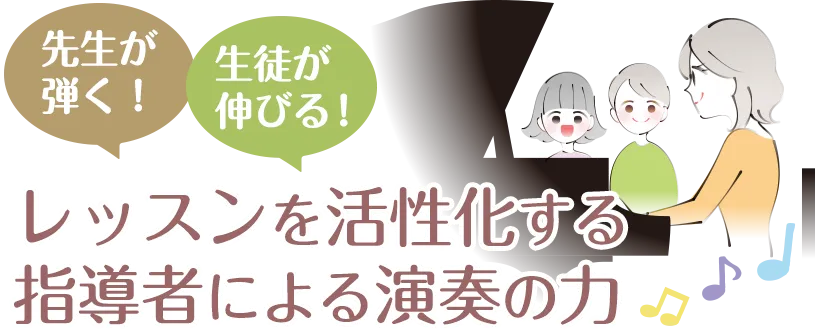
「もっと生徒に音楽の楽しさを伝えたい」「どうすれば表現力が身に付くのだろう?」、そのような悩みの解決は、先生自身の演奏が「鍵」かもしれません。言葉や楽譜だけでは伝えきれない曲のニュアンス、フレーズの息づかい、「音」が持つ表情。これらを生徒に直接届けられるのが、先生の生演奏です。
実際に多くの指導者がレッスンに生演奏を取り入れ、その効果を実感しています。生徒の「聴く力」は飛躍的に向上し、音楽への理解度や意欲が劇的に高まるだけでなく、「先生のように弾きたい」という憧れは、ピアノ学習を長く続けるための大きな原動力にもなるでしょう。
本特集では、指導者を対象としたアンケート結果から見えてきた「先生の生演奏」の現状と、実際にレッスンに生演奏を取り入れている指導者の声を通して、その多角的な価値と可能性を探ります。
今年のピティナ・ピアノコンペティション指導者を対象としたアンケートを行い、コンペに向けたレッスンの中で、指導者が課題曲を演奏することについて、調査を行いました。(回答数:641件)
回答者のうち、99.5%もの先生方が、レッスンの際に、生徒の前で模範演奏されているとの回答が得られました。コンペに向けたレッスンの中では、指導者が演奏して示すことが極めて多いと言えそうです。
| はい(頻繁に演奏する) | 71.4% |
| はい(時々演奏する) | 28.1% |
| いいえ(ほとんど演奏しない) | 0.5% |
| レッスンごとに毎回演奏する | 53.8% |
| 数回に1回演奏する | 16.8% |
| 生徒が特に困っている箇所のみ演奏する | 23.9% |
| その他 | 5.5% |
| 曲全体 | 19.2% |
| 楽章やセクションごと | 32.7% |
| 数小節程度の短いフレーズ | 35.4% |
| その他 | 12.7% |
| 選曲のため、指導する・しないに関わらず課題曲をすべて弾いた | 38.3% |
| 指導した課題曲より多くの曲を弾いた | 33.8% |
| 指導した課題曲すべて弾いた | 20.7% |
| 指導した課題曲の半分以上弾いた | 5% |
| 指導した課題曲の半分未満弾いた | 1.4% |
| ほとんど弾かなかった | 0.6% |

今年のコンペに向けて、生徒が参加する、A1~C級、連弾初級Bの課題曲を弾きました。良い演奏と良くない演奏を弾き比べると、生徒自身の耳で違いを理解する反応がはっきり表れるように思います。普段は、二台ピアノや連弾用楽譜を定期的に購入して生徒とアンサンブルを楽しんでおり、音数が少ない時や、ソロで単調に聞こえがちな曲に取り組む時、和声感を感じてほしい時に、講師がプラスして弾いてあげるとイメージが伝えやすく、生徒のモチベーションや表現を広げることに繋がると感じています。自分が弾けるようにしておくことで、生徒が抱える課題に寄り添うこともできます。一方で自分の癖や好みがそのまま生徒に伝わらないよう、セミナーで他の先生方の演奏や指導を学び、多角的な解釈を取り入れるようにしています。

曲の流れやフレーズを感じ取ってもらうため、演奏を聴かせて気づきを促しています。言葉での指摘を素直に受け止められない生徒には、あえて良くない例をオーバーに弾き、耳で違いを理解してもらう工夫もしています。難易度が上がると自身の練習も必要ですが、部分的にでも一緒に弾くと曲への理解が深まり、視点を変えてアドバイスできます。大人の生徒で「練習は出来ていないが、先生の演奏を聴くために来た」という方もいます。小さい子で一緒の演奏を嫌がる場合には、右手が上達してきた段階で左手で演奏するなど、無理をさせず時期を見極め、自然にサポートすることも心がけています。誕生日に「ハッピーバースデー」をアレンジして演奏したところ、私の誕生日に、メロディーしか弾けなかった生徒が左手の和音を自発的に付けて演奏してくれ、成長を感じる場面もありました。

レッスンで私自身が演奏を示すことで、生徒の音楽への理解と意欲が明らかに変化することを感じています。例えば、課題曲を選ぶ際に複数の候補曲を弾いて聴かせると、生徒自身が曲の雰囲気を具体的にイメージできるようになり、主体的に選曲に関わるようになりました。また、演奏で表現の方向性や音色を示すことで、生徒自身が「聴こう」とする意識が向上するのを実感しています。技術的な指導においても、言葉だけよりも演奏による提示の方が伝わりやすく、特に模倣を通して習得しやすい生徒には効果的です。連弾指導では、私が相手パートを演奏することで、生徒は呼吸感やバランスを肌で感じ、演奏への意欲が向上する場面が多く見られます。連弾では、相手がいない時だけでなく、相手がいる場合でも演奏を提示することで、生徒が客観的に自分の音を聴く意識を持ちやすくなりました。実演の際は、ただ弾くだけでなく、「どこに注目してほしいか」「何を感じ取ってほしいか」を明確に伝えるよう工夫しています。「この部分の拍の流れを感じてみてね」といった声かけをすることにより、受け身ではなく能動的に音楽を聴こうとする姿勢が育っていると感じます。
指導者の演奏力向上・活用コンテンツ
先生ご自身の演奏が、生徒の成長と学習継続に大きく貢献することをご紹介してきました。ここでは、さらにご自身の演奏力を高め、レッスンに活かすためのコンテンツをご紹介します。
eラーニングコンテンツ

コンペ課題曲の指導に役立つeラーニングコンテンツで、曲ごとの演奏ポイントや指導のヒントを深めましょう。実際の演奏を通して、指導の引き出しを増やすことができます。
詳細へコンペ本選・全国大会見学のおすすめ
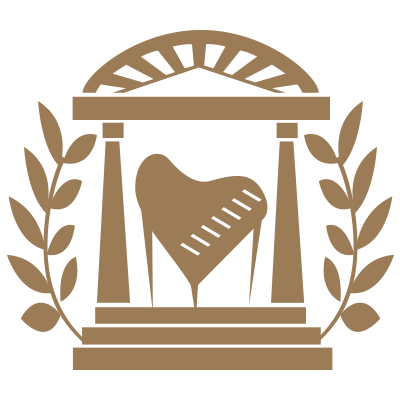
ご自身で課題曲を弾いたからこそ、本選や全国大会の演奏を聴くことで新たな発見があります。生徒の演奏指導のヒントや、表現の幅を広げるためのインスピレーションを得られるでしょう。
詳細へ指導者ライセンス 演奏実技参加のすすめ

ご自身の演奏力を客観的に評価し、さらなる向上を目指しませんか。指導者ライセンスの演奏実技は、日々の努力を形にする機会であり、指導者としての自信にもつながります。
詳細へピアノ教室紹介にご自身の演奏動画を掲載ください

ご自身の演奏動画を教室紹介ページに掲載することで、生徒募集の大きなアピールポイントになります。先生の音楽性や演奏スタイルを伝え、生徒や保護者の方に安心感と期待感を与えましょう
詳細へ